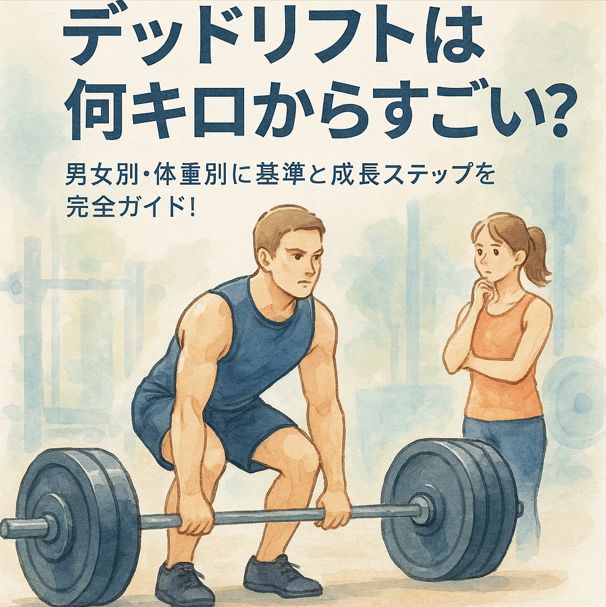デッドリフトは、筋トレの中でも「全身の筋力を試される種目」として人気があります。
特にSNSやジムで他人の記録を目にするたび、「自分はどのくらいのレベルなのだろう?」「何キロ上げたら“すごい”のか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、デッドリフトにおける「すごい」と言われる重量の基準を、初心者から上級者までのレベル別に徹底解説していきます。
また、体重とのバランスやトレーニング経験年数、男女の違いなど、実際の筋トレ現場での評価基準もわかりやすく紹介します。
後半では200kg超えの難易度や、ステップアップのための練習方法・頻度、ケガを防ぐためのポイントにも触れていきます。
デッドリフトの目標設定やモチベーション維持に悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
デッドリフトで「すごい」と言われる重量の基準とは?
体重比1.5倍からが「すごい」の目安
デッドリフトにおいて「すごい」とされる基準には明確な定義はありませんが、多くのトレーニーの間で共通しているのが「体重の1.5倍~2倍」が目安という考え方です。
たとえば、体重70kgの男性なら105kg~140kg、体重50kgの女性なら75kg~100kgをデッドリフトできると、ジム内でも「おおっ!」と注目されるレベルになります。
ただし、この数値はあくまで一般的な目安であり、筋トレ歴や体格、柔軟性によっても変わります。
SNSでは200kg以上を挙げる猛者が目立ちますが、それはあくまでも「ごく一部」のエリート層だという認識を持ちましょう。
比べるべきは他人ではなく、昨日の自分です。
初心者・中級者・上級者の重量分布
筋トレレベル別に見ると、以下のような基準が一般的です。
● 初心者:男性=体重と同じ重量、女性=体重の0.6倍~1倍
● 中級者:男性=体重の1.5倍、女性=体重程度
● 上級者:男性=体重の2倍~2.5倍、女性=体重の1.5倍~2倍
この指標は各ジムやトレーナーによって多少異なりますが、多くの経験者にとって共通する目安とされています。
なお、競技志向のパワーリフターやアスリートになると、体重比で男性3倍・女性2.5倍以上を狙うことも珍しくありません。
ただし、そのレベルに到達するには数年単位の継続的なトレーニングが必要です。
「絶対重量」より「体重比」で評価される理由
同じ200kgのデッドリフトでも、体重60kgの人と100kgの人では評価のされ方が異なります。
筋力は筋肉量に比例しますが、体重が重いほど相対的に高重量を扱うことが可能になります。
そのため、筋トレの世界では「何キロ上げたか」よりも「体重の何倍上げたか」が、実力の指標として重視される傾向にあります。
これはパワーリフティング競技でも同様で、Wilks係数やDOTSスコアといった評価方式も体重比を考慮して算出されます。
つまり、「デッドリフトで体重の1.5倍を持ち上げたら、それはもう十分に“すごい”と言える成果」なのです。
体重別・性別で見る具体的なデッドリフト目標重量
男性の体重別・レベル別目標重量
男性の場合、体重とトレーニング経験に応じて目標となるデッドリフト重量が変わってきます。
以下は一般的な目安です:
● 体重60kg:初心者=60kg、中級者=90kg、上級者=120~150kg
● 体重70kg:初心者=70kg、中級者=105kg、上級者=140~180kg
● 体重80kg:初心者=80kg、中級者=120kg、上級者=160~200kg
● 体重90kg:初心者=90kg、中級者=135kg、上級者=180~220kg
体重が増えるほど、目標重量も上がりますが、それに伴って「体重の2倍超え」は難易度も高くなります。
特に180kg以上のデッドリフトを安定して挙げるには、筋力だけでなくフォームの完成度や体幹の安定も必要になります。
女性の体重別・レベル別目標重量
女性のデッドリフト重量は、筋肉量の違いから男性よりも目標値がやや低めに設定されます。
以下は女性の平均的な目安です:
● 体重45kg:初心者=27kg、中級者=45kg、上級者=70~90kg
● 体重50kg:初心者=30kg、中級者=50kg、上級者=75~100kg
● 体重60kg:初心者=36kg、中級者=60kg、上級者=90~120kg
● 体重70kg:初心者=42kg、中級者=70kg、上級者=105~135kg
体重の1.5倍を目標に据えると、女性でも「かなり強い」と評価される存在になれます。
実際、女性で100kg以上を挙げられる方はジムでも一目置かれる存在になることが多く、SNSでも注目を集めやすいです。
「上位〇%」で見る自分の立ち位置
自身の体重でどれくらいの重量を持ち上げれば、どのくらいのレベルなのかを示す「上位%」という指標も参考になります。
例として、男性体重70kgの場合:
● 132kg → 上位50%(一般的な中級者)
● 170kg → 上位20%(高水準)
● 210kg → 上位5%(非常に優秀)
女性体重50kgの場合:
● 63kg → 上位50%
● 76kg → 上位20%
● 90kg以上 → 上位5%
これらはあくまでも統計的な目安ですが、自分のレベルを客観的に知るうえで非常に役立ちます。
「自分はまだまだ」と感じるかもしれませんが、数字は継続によって必ず変わっていきます。
まずは上位50%を目指し、段階的に目標を高めていきましょう。
初心者がまず目指すべき重量と進め方
最初の目標は「体重=挙上重量」
デッドリフトを始めたばかりの初心者にとって、いきなり高重量を目指すのはケガのリスクが高まるためおすすめできません。
最初のステップとしては、自分の体重と同じ重量を安全に持ち上げることを目標にするとよいでしょう。
たとえば、体重が65kgであれば、まずは65kgのバーベルをフォームを崩さずに3~5回持ち上げられるかを試します。
この段階では「重さよりも正しい動作の習得」が最優先です。
無理に回数を増やすよりも、1回1回を丁寧に行うことが大切です。
ステップアップは「5kg~10kg」ずつが安全
フォームが安定してきたら、次は徐々に重量を増やしていきます。
一度に20kg増やすのではなく、5kg~10kgずつの小刻みなステップアップが安全かつ効果的です。
特に初心者のうちは神経系の発達によるパフォーマンス向上が大きく、数週間の継続で一気に重量が伸びることもあります。
その一方で、フォームが崩れやすくなるのもこの時期なので、トレーニング記録を取りながら「無理のない範囲で増やす」ことを心がけましょう。
また、筋肉痛がある日は無理をせず、休息や軽めのトレーニングに切り替える柔軟さも大切です。
挫折しないための継続テクニック
初心者が挫折しやすい原因のひとつは「成果がすぐに見えにくい」ことです。
実際、フォーム習得期には筋力よりも神経系の発達が中心のため、重量の伸びを感じづらくなります。
そこでおすすめなのが、週ごとの記録をノートやアプリで記録し、自分の成長を「見える化」することです。
たとえば「今日は3回→5回できた」「フォームが安定した」「腰が痛くならなかった」など、重量以外の達成も立派な進歩です。
また、軽い日と重い日を交互に設定する「ライトデー・ヘビーデー方式」を取り入れることで、無理なく長期的に続けることができます。
トレーニングは短期戦ではなく長期戦です。継続できる工夫を重ねていきましょう。
200kg超えはどれくらいすごい?難易度と到達ステップ
200kgの壁は「上級者の証」
デッドリフトで200kgを持ち上げるというのは、一般のトレーニーから見ればまさに「怪物級」の記録です。
実際、男性でもジム通いしている人の中で200kgを挙げられるのは、上位10%未満と言われています。
体重80kgであれば、2.5倍の重量を扱うことになり、全身の筋力・柔軟性・技術が高次元で融合して初めて達成可能です。
SNSでは200kgを挙げる動画も多く見られますが、それはごく一部の経験者に限られた領域です。
焦らず、段階を踏んで確実に成長していくことが大切です。
必要なトレーニング歴と身体能力
200kgを達成するには、少なくとも2~3年以上の本格的な筋トレ歴が必要とされています。
単に背中や脚の筋力だけでなく、次のような能力も必要になります:
● 高い握力と腹圧のコントロール
● 正確なフォームと安定した軌道
● 怪我を防ぐ柔軟性と関節の強さ
● 栄養と休養の徹底的な管理
また、「挙げる筋力」だけでなく「支える筋力」も必要になるため、体幹のトレーニングも重要です。
スクワットやヒップスラスト、ローイングなどの補助種目を組み合わせて、全身を鍛えることが近道となります。
計画的にステップを踏むための方法
200kgという重量は、気合だけで到達できるものではありません。
到達までのロードマップを明確にし、ピリオダイゼーション(周期的負荷調整)を取り入れることが有効です。
たとえば:
● フェーズ①:フォーム安定+130kg程度を目標(3~6ヶ月)
● フェーズ②:体重の2倍となる140~160kg(6~12ヶ月)
● フェーズ③:180kg到達に向けた補助トレ強化(1~2年)
● フェーズ④:200kgチャレンジ(体調管理・記録更新の時期)
記録を週単位で管理し、「何kgを何回できたか」「疲労度はどうだったか」などのデータを蓄積することで、改善点や壁の原因が見えてきます。
過去の自分を超えていく意識が、200kgという“高み”への道を切り拓いてくれるでしょう。
スポンサーリンク
ケガを防ぎながら記録を伸ばすポイント
ウォーミングアップとフォームが最優先
デッドリフトは高重量を扱う種目のため、フォームの乱れや準備不足は即ケガにつながります。
そのため、まず最も大切なのが「ウォーミングアップ」と「正確なフォームの習得」です。
トレーニング前には5~10分の軽い有酸素運動(バイクやウォーキング)で全身を温め、その後、軽めのバーベルを使ってフォーム確認を兼ねた動作練習を行いましょう。
特に背中が丸くなったり、膝が内側に入るようなクセは腰痛や膝痛の原因になるため、動画撮影などを活用して客観的にチェックするのがおすすめです。
慣れないうちは、ジムのトレーナーや経験者にフォームを見てもらうのも良い方法です。
オーバーワークを避ける頻度とセット管理
デッドリフトは消耗が激しいトレーニングのため、週2回の頻度が基本とされます。
初心者は週1回でも十分で、フォームの安定と体の回復に重点を置きましょう。
また、1回あたりのトレーニングも「3~5セット」「1セット5~8回」程度が目安です。
限界ギリギリまで追い込むのではなく、「2回ほど余力を残す」くらいの強度で行うと、怪我のリスクを大きく減らせます。
筋肉痛や倦怠感が強い日は無理せず休む、または他部位のトレーニングに切り替える柔軟性も重要です。
ギア・栄養・睡眠を含めた“トータル管理”
高重量を扱うデッドリフトでは、補助ギアの使用もケガ予防に効果的です。
たとえば:
● パワーベルト:腹圧を高め、腰部の安定感を向上
● リストストラップ:握力の消耗を抑え、背中への意識を強化
● フラットなトレーニングシューズ:足裏感覚をつかみやすく、安全な重心操作が可能
さらに、食事や睡眠もトレーニング効果を最大化するために欠かせません。
タンパク質(体重×2g/日)を基本に、炭水化物でエネルギー補給、ビタミンやミネラルで回復を促進させましょう。
また、1日7~8時間の睡眠を確保することで筋肉の修復もスムーズになります。
「トレーニング・栄養・休養」の三位一体のバランスが、デッドリフトで長期的に結果を出すための土台となるのです。
まとめ
体重比で見る「すごさ」の基準を知ろう
デッドリフトにおいて「何キロからすごいのか?」という疑問には、絶対的な答えはありません。
しかし、体重の1.5倍~2倍を上げられれば、多くのトレーニーの中でも確実に「すごい」と評価されます。
特に200kgを超える重量は、上級者の証であり、数年単位の努力の成果とも言えます。
性別・体重・レベル別に目標を設定する
自分の体重を基準に「まずは1倍」「次に1.5倍」と段階的な目標を立てることが大切です。
男性も女性も、それぞれに応じた成長の道筋があり、焦らず着実にステップアップすることが記録更新への近道となります。
レベル別の目安を知っておけば、自分の立ち位置や次に目指すべき数字が明確になります。
安全第一で、長く強くなろう
デッドリフトは高重量を扱う分、正しいフォームと安全管理が欠かせません。
ウォーミングアップや補助ギア、栄養・睡眠といった基本を大切にしながら、怪我なく継続していくことが大切です。
数字ばかりに気を取られず、「昨日より少し強い自分」になることを目指して取り組んでいきましょう。
あなたの努力が、必ず次の“すごい”記録につながります。
スポンサーリンク